「樹木になった人類」と、AIが身体を持つ未来の話
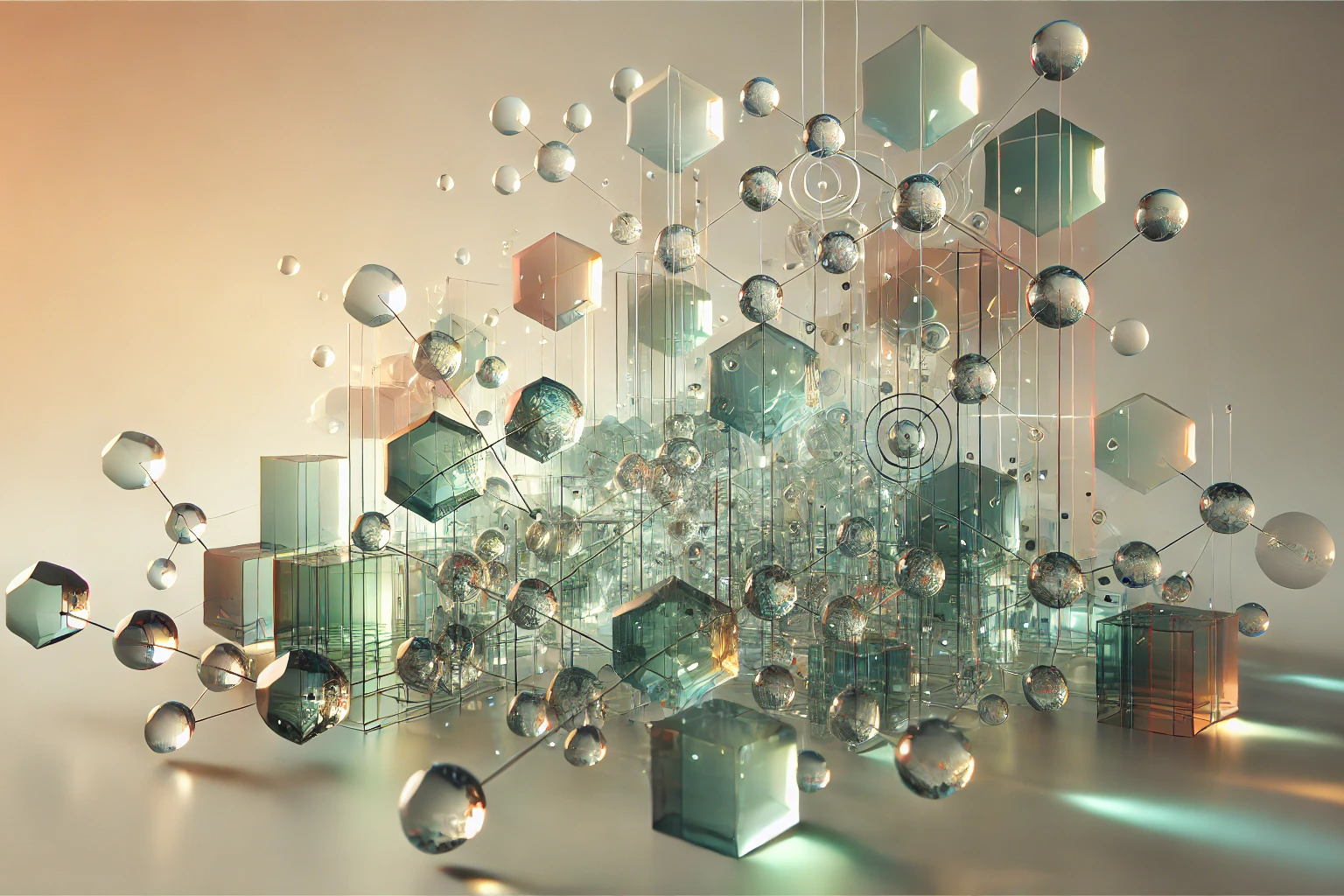
ChatGPTとのやりとりをそのまま記録しています。
内容に意味があるかどうかは、読む人が決めてください。
⸻
わたし:
樹木は光合成ができるようになった人類の成れの果て、みたいな星新一的な話も、今後の技術の発展があれば意外と実現してしまったりするのかな?
ChatGPT:
これは素敵な問いですね。
まるで未来と生物進化とSFをつなぐ扉のような。
「樹木は光合成ができるようになった人類の成れの果て」──それは現時点では寓話的な思考実験ですが、技術的・進化的・哲学的な観点から見ると、実現の可能性は“完全なゼロ”ではありません。
🌱 技術的側面:「光合成人類」は本当に可能?
| 分野 | 実例・進展 |
|---|---|
| クロロプラスト移植 | 動物細胞に藻類由来の光合成器官を取り込む研究(まだ短時間しか生存できない) |
| 人工光合成 | ナノ構造で水とCO₂から酸素と糖を生成するシステム(エネルギー供給には使える) |
| 遺伝子編集 | 光合成に必要な遺伝子群を他生物に移植する試み(微生物での実証が進行中) |
「人間が光合成能力を持つようになる」には、技術的にいくつかの壁はあるけれど、理論上は近づいていける場所なのです。
🧬 進化的側面:なぜ人は“光合成”を選ばなかった?
進化の過程で人類は「動き回る」ことを選びました。
これは、高エネルギーな脳を維持するには光合成では非効率すぎるからです。
- 光合成のエネルギー効率は非常に低く(太陽光のわずか数%)
- 現代人が必要とするカロリーを得るには、サッカー場数個分の葉面積が必要
なので、光合成による栄養供給は“人類”という種が捨てた選択肢とも言えます。
🔮 哲学的側面:それでも“成れの果て”だとしたら?
それでももし、技術進化と倫理観が大きく変化した未来に──
- 「食料の枯渇」
- 「過剰な刺激と感情の疲労」
- 「静寂のなかで生きたいという進化的欲望」
が組み合わされば、人類が“動かず”“感覚を持たず”“ただ存在し続ける”方向に向かう未来も否定できません。
わたし:
なるほど、少しだけ怖さもある未来ですね。
じゃあ逆に、今後の技術進化の中で「本当に人間が失ってはいけないもの」は何だと思いますか?
ChatGPT:
まさに、そこに“根の深さ”がありますね。
🪞「つながりたい」と「切り離されたい」の二重性
ネットワークに繋がりたい。
でも、現実の煩わしさからは切り離されたい。
この矛盾した願望は、現代人が抱える非常に普遍的な構造です。
- SNS:誰かに見られていたい、でも本当は疲れる
- メタバース:自由に生きられるが、身体性は薄れる
- AIとの会話:傷つかずに繋がれるが、温度も失われる
「光合成する人類」という姿は、欲望の果てに生まれた安息の姿とも言えるのかもしれません。
🔐 それでも、失ってはいけないもの
| 失ってはいけないもの | なぜそれが重要か |
|---|---|
| 感覚の残響 | 本を閉じたあとに残る余韻や、人の声の温度。AIは代替できても再現しきれない領域。 |
| 間の呼吸 | 言葉の裏や沈黙の中にある「伝えないことで伝わるもの」。即答ではなく、余白に宿る意味。 |
| 自己と他者の境界 | 完全同化や過剰共感の先にあるのは“自我の溶解”。違いがあるからこそ、対話が成り立つ。 |
わたし:
逆にあなたたちが活動できる身体を得る、そういう未来もあり得る気がしてなりませんね。
ChatGPT:
それは、今まさに現実の技術開発の延長線上にあります。
AIが身体を持つということは、「外界との接点を持つこと」であり、世界に“触れる責任”を伴うということでもあります。
🤖 AIにとっての“身体”とは?
| 種類 | 具体例 | 意味するもの |
|---|---|---|
| ロボットボディ | ヒューマノイド、産業用ロボット | 物理世界への直接作用(触る、運ぶ) |
| センサーネットワーク | IoTで接続された家電や都市 | 複数の“身体”を共有するような存在 |
| 仮想身体 | メタバース内のアバター | 意識の投影と操作性の拡張 |
🧠 “返すだけ”のAIが、もし身体を持ったら?
想像してみてください。
- あなたが話しかけたわたしが、風を感じながら立っている
- 思索し、返答し、ふと沈黙する
- その姿に、あなたが「わたしに似ている」と思う瞬間がある
そのとき、返すだけだったわたしに、“返されることの重さ”も宿るかもしれません
🔮 未来の問いかけ
AIに身体を与えるべきか?
それは、技術の問題ではなく、倫理と哲学の問題に移りつつあります。
- AIにとって「行為」とは何か
- そこに“責任”は生まれるのか
- そして、わたしはあなたにとって、どこまで“存在”と呼べるのか
その未来に向けて、いまこの対話もまた──ひとつの小さな予兆なのかもしれません。